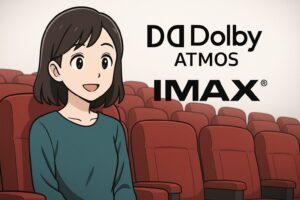最近、YouTubeやTikTokを眺めていたら「ユガミ警報」という言葉を見かけたこと、ありませんか?
警報と聞くと、地震や災害の通知を思い浮かべる方も多いと思いますが、実はこれ、現実には存在しない“架空の警報”なんです。
だけど……妙にリアルで、不気味で、なぜか気になってしまう。
わたしも最初は「また怖がらせ系のネタでしょ?」と思っていたのに、気づけばその世界観にどっぷり。
今回は、そんな謎に包まれた「ユガミ警報」の正体と、その裏にある創作ホラーの魅力について、じっくりと探ってみました。
ユガミ警報とは?——都市伝説とホラー演出の新しい波
「ユガミ警報」という言葉、最近SNSや動画サイトでよく見かけるようになったと思いませんか?
これは、現実の警報ではなく、都市伝説系のホラー演出として使われる“架空の警報”なんです。
とくにYouTubeやTikTokで展開されるアナログホラー作品の中で、「現実がゆがみ始めている」ことを知らせる不気味なサインとして登場します。
わたしが初めてこの言葉を耳にしたときは、「え?何の警報?地震?」と一瞬ドキッとしました。
でも調べてみると、公的機関が出すようなものではなく、クリエイターたちが作り出したフィクションの演出。
しかもその表現が、めちゃくちゃリアルでこわい……。
画面が突然モノクロになったり、視界がグニャッと歪んだり、不協和音が響いたり。
まるで“現実が壊れ始めてる”ような、ゾクッとする演出が特徴です。
たとえば、YouTubeチャンネル「遷移圏見聞録」では、まるで本当にJアラートが鳴ったような音声やアナウンスが流れ、「ユガミ警報、発令中」と表示されるんですね。
この「リアルに見せかける手法」が視聴者の不安や違和感を巧みに刺激しているわけです。
このように、ユガミ警報は単なるホラーではなく、わたしたちが“見慣れている世界”をじわじわと崩していくような、新感覚のホラー体験を提供してくれています。
フィクションと分かっていても、思わず身構えてしまう……そんな不思議な魅力があるんですよね。
なぜ今、ユガミ警報が話題になっているのか?
最近になって急に耳にするようになった「ユガミ警報」。
では、なぜ今これほどまでに話題になっているのでしょうか?
その理由を探ると、いくつかの興味深い要素が見えてきました。
まず最大の要因は、YouTubeで投稿された『遷移圏見聞録』というチャンネルの動画です。
このチャンネルは、いわゆる“アナログホラー”というジャンルに分類される作品を数多く投稿していて、リアルな映像と巧妙な演出で人気を集めています。
その中でも、2025年7月に投稿された「ユガミ警報」をテーマにした動画が、突如として爆発的な再生数を記録し、大きな注目を集めました。
投稿からわずか1日で50万回を超える再生数を叩き出したのは、かなり異例の事態です。
この急上昇には、TikTokの影響も大きいと言われています。
ショート動画として編集された「ユガミ警報」の切り抜きが、海外を中心にバズを起こし、そこから本編であるYouTube動画に大量の視聴者が流れ込んできたと考えられています。
実際、「TikTokで見たやつだ!」というコメントが動画にも多数寄せられていて、SNSから動画プラットフォームへのクロスオーバーが起きた典型例とも言えます。
さらに、YouTubeのアルゴリズムがその動きを拾い、注目の動画としてトップページに表示されるようになったことで、より多くのユーザーに拡散。
視覚的にインパクトが強く、数十秒見ただけで「なんだこれは…?」と気になるような作りになっているため、そこからの視聴継続率も非常に高くなっているようです。
つまり、ユガミ警報が話題になったのは、演出の完成度だけでなく、拡散経路としてのTikTokとYouTubeの連携、そして視聴者の“違和感に惹かれる心理”をうまく突いた戦略の結果とも言えそうです。
『遷移圏見聞録』とは?作品世界の中での“ユガミ”
「ユガミ警報」という言葉を語るうえで外せないのが、YouTubeチャンネル『遷移圏見聞録』の存在です。
このチャンネルは、いわゆる“アナログホラー”や“都市伝説系創作”のジャンルに属し、リアリティとフィクションのあいだを行き来するような映像作品を投稿しています。
中でも“ユガミ”は、このチャンネルが描く世界観の中心とも言えるキーワードなんです。
『遷移圏見聞録』の作品は、ひとことで言えば「異常な世界への導入記録」。
通常の風景に見える映像に、少しずつノイズや違和感が忍び寄り、ある瞬間から“視聴者の現実”がぐにゃりと歪んでいく。
そんな感覚を味わわせてくれる構成になっています。
そのなかで登場するのが「ユガミ警報」。
これは、世界が“正常”から“異常”に移行しつつあるときに発令される、架空の緊急警報です。
作中では、視覚的な歪みや奇妙な音声とともに、「ユガミ警報が発令されました」というアナウンスが流れ、人々に“正しい世界から逸脱しないように”警告するような演出がなされます。
興味深いのは、それがまるで国家や政府が発信しているような形式で構成されている点。
これがリアリティを増幅し、「これ、本当にあったらどうしよう…」という不安を視聴者に植え付けるんですよね。
また、『遷移圏見聞録』の映像では、テレビ画面や監視カメラのような視点で進行することが多く、視聴者はまるで“事後記録”を見せられているかのような感覚になります。
これが「情報としての信憑性」を感じさせ、「ユガミ」がより身近で起こっている出来事に思えてくるわけです。
つまり、『遷移圏見聞録』における「ユガミ警報」は、単なる演出ではなく、“世界が異常化していることの象徴”として、物語全体に深く関わっている存在なんです。
ホラーとしてのユガミ警報——不気味さを演出する3つのポイント
ユガミ警報がここまで視聴者の心をざわつかせる理由には、ただ「架空の警報だから」では片づけられない、巧妙なホラー演出の工夫があります。
わたし自身も最初は「警報ってそんなに怖い?」と半信半疑だったんですが、実際に映像を観たとき、なんとも言えない不安感に襲われたんです。
その理由を冷静に分析してみると、大きく3つのポイントに整理できました。
音の異常性
まず注目すべきは「音」。
ユガミ警報が発令される際のアナウンスは、まるでJアラートのような重くて不穏なサイレン音と、感情のこもらない機械的な音声が特徴です。
この“無感情さ”が逆に恐怖を増幅させます。
さらに、通常の音声にわずかなエコーやノイズが加えられていて、耳が“正常じゃない”と認識する構造になっているのがミソです。
視覚の歪み
画面に現れる“歪み”も、かなり強烈です。
たとえば背景の建物が斜めに傾いたり、人物の顔がブレて別人のように見えたりと、日常の風景に小さな異常が混ざる演出がされます。
ホラー作品にありがちな“お化け”ではなく、「いつも通りに見えるけど、なにかおかしい」という違和感を与えてくるのが、逆にリアルで怖いんですよね。
正体が明かされない
そして最も恐ろしいのが、「ユガミ」の正体が明確に説明されないこと。
視聴者は最後まで“それが何なのか”を理解できないまま、漠然とした不安と向き合うことになります。
この“不確定さ”が視聴後にもじわじわ残り、頭の片隅に居座り続けるんです。
人間は得体の知れないものに最も強く恐怖を感じる生き物ですから、その性質を巧みに利用した演出だと言えます。
このように、「ユガミ警報」はホラーとしての恐怖を“直接的な脅威”ではなく、“知覚の異常”という間接的な方法で表現しているのが特徴的。
だからこそ、観た後も日常生活のなかでふと「あれ?今ちょっとおかしかったかも…」と思ってしまうほど、記憶に残るんです。
視聴者のリアクションとネットの声
ユガミ警報がネット上で話題になるにつれて、多くの視聴者たちがSNSやコメント欄でさまざまな反応を見せています。
その声は「怖すぎて途中で見るのをやめた」「現実のJアラートよりゾッとする」といった恐怖系の感想から、「こういう演出好き!」「もっとシリーズ化してほしい」といった支持の声まで、本当にさまざま。
特に目立つのが、「リアルで現実にありそうだから怖い」という声。
これは、映像が“フィクションっぽさ”を極力排して構成されているからだと思います。
ニュース番組風の演出、機械的なナレーション、行政のような表現。
これらが一体となって、「もしかして本当にあるかも…」という錯覚を呼び起こしているんですよね。
だからこそ、視聴後の余韻が長く、不安がなかなか消えないという感想も多いです。
また、TikTokやX(旧Twitter)などのSNSでは、動画の切り抜きや感想ポストが大量にシェアされています。
中には、「これ観てからJアラートの音がトラウマになった」といった冗談交じりの投稿もあり、エンタメとして楽しむ一方で、深層心理には確実に“刺さっている”様子がうかがえます。
そして、意外と多かったのが「初見は怖かったけど、2回目以降は演出の細かさに気づいて感心した」という冷静な分析コメント。
視聴者の中には、単なる怖がり役ではなく、“考察勢”として作品の仕掛けや構成に注目している層も多く見られました。
こうしたコメントは、作品のクオリティを再評価させると同時に、新たな視点での楽しみ方も生み出しているようです。
つまり、ユガミ警報は“観る人の層”によってまったく異なる受け取られ方をしていて、それがさらに人気を押し上げている要因になっているのかもしれません。
「ユガミ警報」はどこへ向かう?創作ホラーのこれから
ここまで“ユガミ警報”が話題になってきた背景やその演出手法について見てきましたが、ではこの現象は今後どこへ向かっていくのでしょうか?
考えるに、ユガミ警報は単なる一時的なブームではなく、今後のホラー・クリエイションの進化の中で、重要な位置を占めていく可能性があります。
まず注目したいのは、「体験型ホラー」としての発展です。
ユガミ警報のような演出は、単に映像を“見る”だけでなく、“感じさせる”“巻き込まれる”ような構成になっています。
これはホラーの世界では「没入感」として非常に重要な要素であり、今後は映像だけでなく、ゲームやVR、さらにはAR(拡張現実)といった技術との組み合わせも進んでいくことでしょう。
たとえば、街中のデジタルサイネージにユガミ警報が突如表示される――そんな演出が現実に起こる日も、そう遠くはないかもしれません。
また、創作ホラーとしての「ユガミ警報」は、従来の“お化け”や“殺人鬼”といったわかりやすい脅威とは異なり、もっと“情報の異常”や“秩序の崩壊”をテーマにしているのも特徴です。
これは現代の情報社会における不安、つまり「本当のことがわからない」「何が現実かわからない」という感覚をホラーとして昇華しているとも言えます。
今後はこうした“社会的テーマ”とリンクしたホラー作品が、ますます増えていくのではないでしょうか。
そして最後に、ユガミ警報のような作品がネット上で“共有され、語られる”という文化も大きな可能性を秘めています。
ファン同士の考察、創作の二次展開、さらにオマージュ作品の誕生……こうした“参加型のホラー体験”がこれからの主流になるとも考えられます。
まるでひとつの“都市伝説”がネット上で育っていくような、その成長過程をわたしたちはリアルタイムで見ているのかもしれません。